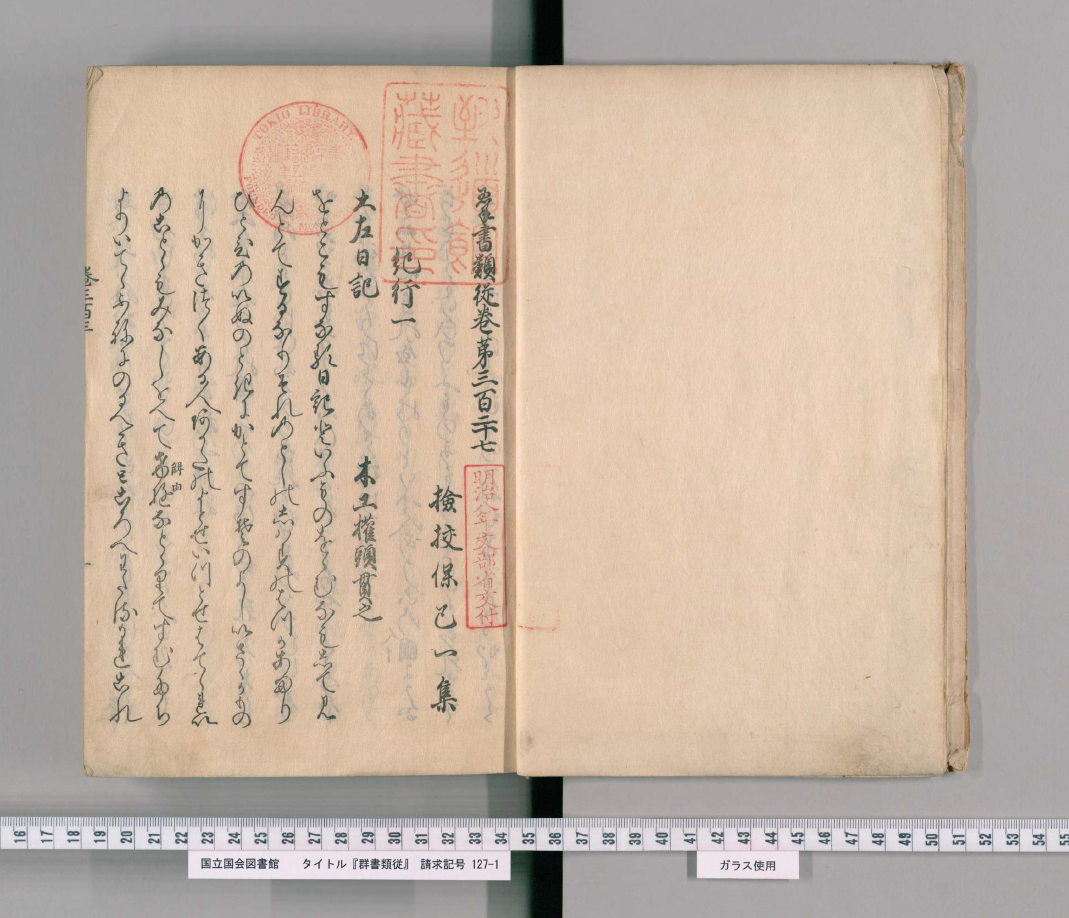はじめに
皆さんは「ビジネス」と聞いて何が思い浮かぶだろうか。
日本ではしばしば、この言葉が悪徳商法を指すものとして用いられる。
ネットワークビジネスに取り組む者が好んでこの言葉を使用することが主な要因であろう。
事実、現代のあらゆるコミュニティにおいて有害な「ビジネス」の紹介者は観察される。
そこで今回は、社会人サークルでのマルチ商法勧誘の実態に焦点をあて、問題点を探っていくこととする。
なお、社会人サークルといえばひと昔前まではマルチ商法の温床でかなりイメージが悪かったが、今日では運営会社が主催者と参加者を仲介し、厳しい監視の下イベントを開催するのが一般的である。そのため現在は直接的に勧誘を受けることは無い(あれば即座に運営へ通報される)。
特徴
⑴権利収入が手に入ると謳う。ここで言う権利収入とは、自分が紹介(勧誘のことを紹介と呼ぶ)した人間が更に別の人間にビジネスを紹介するという連鎖により、何もしなくても紹介報酬が入ってくる状態になること。
⑵製品への絶対的信仰心がある。景品表示法や薬機法のせいではっきりとは言えないが、実はアトピーが治る、体調がよくなるなどと発言する。
⑶究極の自責思考を持つ。成功しないのはすべて自分側に問題があるとし、自らの行動を恥じ、具体的な数字目標を挙げて組織に従っていれば必ず成功が訪れると信じている。
⑷友達を失わせる。よく「マルチ商法は友達を失う」という言説が取り沙汰されるが、これは組織側が、「利害関係の無い友達は不要で、ともに高めあえる仲間がいればよい」と言って勧誘をさせるためである。故にビジネスに取り組んでいる友達に辞めたらどうかと提案しても、それはビジネスに目覚めていない哀れな人間の発言としか受け止められない。
⑸お金を失わせる。商品やセミナーが高価だと感じ、そう伝えても、権利輸入の対価としては破格のものだと一蹴される。
⑹夢100を書かせる。夢100とは、実際に入手できるかを考慮せずに自分がほしい・家族にプレゼントしたいモノ・コトを100個列挙すること。ここに挙げたモノ・コトは常に頭の片隅に置かれることとなり、いつまでに手に入れる、と期間を定めることで、潜在意識により最終的にすべて手に入るようになると言われている。
誘い方
今日の勧誘方法は、旧来のそれに比して非常に複雑である。これは特定商取引法により勧誘目的を隠してのイベントへの招待が禁じられたこと、世間でのネットワークビジネスの印象が大きく悪化したことが主な原因である。
⑴社会人サークルのイベント
①勧誘者はまず、不特定多数の参加者がいるイベントに一般人と同じように参加する(ここでは社会人サークルの運営サイトから参加申し込みをしたと想定する)。
②参加中は他の参加者と積極的に交流を図り、連絡先を交換する。
〈注意点〉
・連絡先を交換する人はなるべく「誠実な人」、すなわちフッ軽な人、断るのが苦手な人、および真面目に話を聞いてくれそうな人に限定する。これはこの先の進行に影響を与える。
・連絡先の交換は基本的にLINEで行なう。イベントの運営サイトに独自のメッセージツールが用意されている場合もあるが、これを用いるとその後の勧誘がサイトの規約に違反していたときにBANされる恐れがある。
⑵勧誘組織のイベント(1回目)
①⑴のイベント中またはイベント後に、運営サイトに載っていないイベント(勧誘者の所属する組織が開催するイベント)に参加しないかと誘う。
②OKがもらえたら、当日は2人で、会場近く(大半は駅)で待ち合わせをする。
③このイベントでは、特に何か勧誘することはしない。代わりに転職の検討など何かしら将来への不安がないかを聞き、良ければその悩みを聞いてくれる人(大半は経営者)がいるので今度紹介すると話す。
④同じ組織の次回開催のイベントに参加させるためアポを取る。
〈注意点〉
・主催する組織の存在は明かさない。あくまで一般的なイベントを装い、警戒心を持たれないようにする。
・待ち合わせ場所を会場にしない。被勧誘者と同行して会場入りすることで、実態不明のイベントに参加する被勧誘者の不安の払拭を図る。
⑶勧誘組織のイベント(2回目)
①件の経営者と直接話をさせる。
②2人でその人に相談しに行こうと提案する。
〈注意点〉
・①ではまず被勧誘者を経営者に紹介し、将来のことで不安があるようで……と伝える。
⑷三者面談
①2人で、会場近くで待ち合わせをする。
②会場(経営者が住んでいるまたは事務所としているタワーマンションが選ばれることが多い。そこにいられるだけの収入が得られるのだと示すため)に行き、経営者に話をしてもらう。
③セミナー参加の話があるので、アポを取る。または経営者の弟子との面談を追加で組む。
〈注意点〉
・三者面談では経営者が事前に用意してきた話をするため、特に勧誘者が話すことは無い。なお三者面談で話される内容はビジネスの必要性およびビジネスを始めてから成功するまでのおおまかな流れで、より詳細な説明・ビジネスの始め方は別途セミナーに参加する必要があると伝えられる。
・組織の正式名称は出さない。ただし特定されない程度にアルファベット等による略称を用いることは妨げない。特にマルチ商法の場合、企業名が非常に悪いイメージとともに広まっているケースが多いため。
・被勧誘者側からセミナー参加したいと表明させる。本当に詳しく話を聞きたいと思っている人しかセミナーに参加させていないが参加するか?といった聞き方でよい。これによってセミナーは被勧誘者自らの意思で参加したことになり、事業者名もセミナー時に明かすため、これで特定商取引法上の制限は回避できる。
・会場での着席位置は、経営者が奥の席に座るので、その真向いに勧誘者が、斜向かい(勧誘者の隣)に被勧誘者が座るようにする。こうすることで被勧誘者の心理的圧迫感を減らすことができる。
・経営者が話しているときは頷く、あいづちを打つなど共感の態度を見せ、面談終了後は「スゴくない!?」「ヤバくない!?」といった情動を煽る感想を伝え、また引き出す。
⑸セミナー
①2人で、会場近くで待ち合わせをする。
②会場(比較的規模の大きい、都心のレンタルスペースや公民館が選ばれることが多い)に行き、セミナーを受講する。
③以降、所属組織の案内に従ってセミナー等に参加させる。
〈注意点〉
・この段階ではじめて正式な企業名をオープンにするため、被勧誘者がその名前を知っていたりして抵抗感を示したときは、その後の話を聞けば印象が変わると伝えたり、場合によっては勧誘を諦めるなど慎重かつ柔軟な対応を取る。
社会人イベント運営会社側の対策
例として筆者がよく利用している「つなげーと」での禁止事項を挙げる。

https://tunagate.com/articles/rules/guidelines/c89f9582?ifx=AloyZb77v57mKQDx
これを見ると、今日の勧誘方法は、法律違反こそせずとも、運営サイトの規約までは守れていないのが明確である。
しかしながら、現実的には、規約違反を理由に勧誘者を運営に通報することは難しい。なぜなら、前述のように勧誘者は被勧誘者と対面でLINE交換をし、そこで外部イベントに誘っているので、勧誘している証拠がないのである。
被勧誘者側の対策
⑴外部イベントに招待してくる人間は勧誘目的を疑う。一対一での食事や一般向けの音楽フェスなどの招待であればまだ勧誘リスクは低い(ただし食事をする店が、ビジネス関係者の運営する店だった、というパターンも多いため注意が必要)
⑵将来の仕事について相談に乗る、という人間とはイベント外で接触しないようにする。本当に相談に乗ってくれているだけの可能性もあるが、それ以上に勧誘してくる割合の方が高い。
⑶ビジネスの話が出た時点で、すでに自分も取り組んでいる、と伝える。どの企業のものか問われる可能性があるので、有名なネットワークビジネス起業の名をいくつか把握しておくとなおよい。
⑷運営サイトの規約に違反していると伝える。サイト経由でのイベント参加時には最も効果的だろう。
おわりに
筆者はもともと将来への漠然とした不安があり、それを解消するべく人間関係を広げて見聞を深めようと社会人サークルを利用するようになったという経緯がある。
そんな心の隙間に勧誘者側は器用につけこんでくる。そういった勧誘にひとたび引っかかってしまえば、たとえ合法的な活動であろうとも、多くのものを失うことは避けられない。
人との関わり方が多様化している現代だからこそ、断る力は重要だと言える。